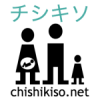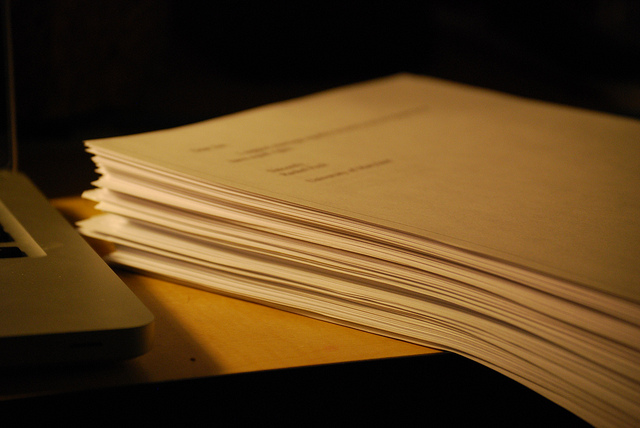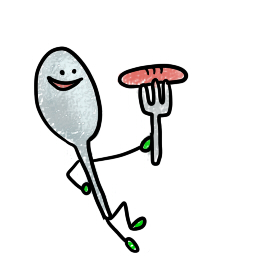仕事をする上で文書を作る機会は多くありますよね。
いざ文章を書き出すとき、内容は決まっていても導入部分としてまずは季節に応じた挨拶を・・と思って書こうとしても、思いつかない!無駄に時間をとってしまいます。
言いたいことは違うことなのに、冒頭部分で悩む時間って本当にもったいないです。
ここではビジネスでも使える文章の冒頭部分にぴったりな時候の挨拶を月別に一覧したものと共に、ビジネス文書の基本の書き方ももまとめました。
ぜひ参考にしてくださいね!
時候の挨拶月別一覧
まずは時候の挨拶を月別にまとめます。ひと月に4つづつ紹介していますので、文章を作っている季節によって下記の時候の挨拶の中からいいなと思うものを一つ選んでみてください。
後半で紹介している文章の書き方に当てはめれば迷わず文章がつくれます。
時候の挨拶【1月】
- 初春の候
- 新春とは名ばかりの寒さが続きます
- 本格的な冬の到来です
- 寒さ厳しきおりから
時候の挨拶【2月】
- 春寒の候
- 早春のみぎり
- 立春とはいえ寒さが残るこの頃
- 梅のつぼみもふくらみ始める頃
時候の挨拶【3月】
- 浅春のみぎり
- 桃の節句を迎え
- 春寒もゆるみ
- 一雨ごとに春めいてまいりました
時候の挨拶【4月】
- 陽暖の節
- 陽春の候
- 花の便りも聞こえ
- 野に春の香り漂うこの頃
時候の挨拶【5月】
- 新緑の候
- 新緑したたる好季節
- 雲ひとつない五月晴れのこの頃
- 青葉若葉が目にしみる頃
時候の挨拶【6月】
- 梅雨の候
- 初夏の節
- 梅雨明けが待たれる毎日
- さわやかな初夏
時候の挨拶【7月】
- 盛夏の候
- 本格的な夏となりました
- 蒸し暑い日が続いております
- 夏空のまぶしい季節
時候の挨拶【8月】
- 残暑の候
- 立秋の候
- 夏も盛りを過ぎ
- 立秋とはいえ厳しい暑さが続きますが
時候の挨拶【9月】
- 初秋の節
- 朝夕の風はめっきり秋らしくなり
- さわやかな季節となり
- 空高く澄みわたるころ
時候の挨拶【10月】
- 仲秋のみぎり
- 紅葉の季節となり
- 菊花薫るおりから
- 秋も深まり
時候の挨拶【11月】
- 晩秋の節
- はや冬も近づき
- 穏やかな小春日和が続きますが
- 木々の葉も散り行く頃
時候の挨拶【12月】
- 寒冷の候
- 歳末多忙のおりから
- 年内もあとわずかになりました
- 木枯らしの身にしみる頃
時候の挨拶を使った文章の書き方(構成)
ビジネスに使える文章の型を知る
| 1.頭語 | ||
| 前文 | 2. | 時候の挨拶 |
| 3. | 安否の挨拶 | |
| 4. | 感謝の挨拶 | |
| 5.主文 | ||
| 6.末文 | ||
| 7.結語 | ||
この流れをまず知ることだけでも相当な時間短縮になります!
頭語と結語よく使うもの
| 1.頭語 | ||
| 前文 | 2. | 時候の挨拶 |
| 3. | 安否の挨拶 | |
| 4. | 感謝の挨拶 | |
| 5.主文 | ||
| 6.末文 | ||
| 7.結語 | ||
時候の挨拶に入る前に、まずは頭語と結語をセットで考えましょう。
この表で言うと赤い部分ですね。よくある「拝啓」とかの部分です。
場合や人によって使い分けます。
- 丁寧に書きたいとき「謹啓」ー「謹言」
- 一般的な場合「拝啓」ー「敬具」
- 急いでいる場合「急啓」ー「敬具」
- 前文省略の場合「前略」ー「早々」
- 初めて出す手紙の場合「突然で失礼とは存じますが」ー「不一」
- 親しい人へ「お元気ですか」ー「ではまた」,「こんにちは」ー「ごきげんよう」
- 返信の場合「拝復」ー「敬具」
ビジネスで使用する場合は
丁寧に書きたいとき 「謹啓」ー「謹言」
一般的な場合 「拝啓」ー「敬具」
のあたりがよく使う頭語と結語です。
※「前略」ー「早々」は挨拶を省略するということ。
丁寧な文書とは言えませんので目上の方やお詫びなどの場合は使わないようにしましょう。
続いて、前文の部分を見ていきましょう。
前文:ここで時候の挨拶!月別一覧から決めたものを使用
| 1.頭語 | ||
| 前文 | 2. | 時候の挨拶 |
| 3. | 安否の挨拶 | |
| 4. | 感謝の挨拶 | |
| 5.主文 | ||
| 6.末文 | ||
| 7.結語 | ||
前文は「時候の挨拶」「安否の挨拶」「感謝の挨拶」に分かれます。
時候の挨拶とは、季節の天候や状況などを表現する挨拶。表で言うと2の部分になります。
これを書くことで、文書に季節感が生まれ丁寧な文書が出来上がります。
この時候の挨拶にはパターンがあります。先ほど紹介した「時候の挨拶月別一覧」から選んだものを使います。
安否の挨拶のパターン
時候の挨拶を入れたら、次に安否の挨拶を入れます上記の表で言うと3の部分です。
「ますます●●●のこととお慶び申し上げます。」
という形が一般的です。
「●●●」の部分は、個人か組織かで使い分けましょう。
使い分け方はこちら。
(個人の場合) ご健勝 ご清栄 ご活躍 ご清祥
(組織の場合) ご隆盛 ご繁栄 ご発展 ご隆昌
感謝の挨拶のパターン
続いて、上記の表4の部分に入れる感謝の挨拶についてです。
一般的な例は以下の通りです!これもどれかを選んで書けばいいですよ。
- 平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
- 日頃は多大なるご厚情を賜り厚くお礼申し上げます
- 毎々格別のお引き立てをいただき有難く厚くお礼申し上げます
ここまで書けたら、次は今回の主文を入れます。
時候の挨拶を含む前文がかけたら主文に入る
| 1.頭語 | ||
| 前文 | 2. | 時候の挨拶 |
| 3. | 安否の挨拶 | |
| 4. | 感謝の挨拶 | |
| 5.主文 | ||
| 6.末文 | ||
| 7.結語 | ||
前文が書けたら、本題に入ります。
改行して、「さて」「このたび」「早速ですが」を使って本来の内容を書き始めましょう。
ここは、言いたいことを書く部分。決まり切った言葉よりもしっかり自分の言葉で書く方が伝わるります。丁寧さを心がけて書くようにしましょう。
6.末文
| 1.頭語 | ||
| 前文 | 2. | 時候の挨拶 |
| 3. | 安否の挨拶 | |
| 4. | 感謝の挨拶 | |
| 5.主文 | ||
| 6.末文 | ||
| 7.結語 | ||
表の6番の部分です。
主文で今回伝えたい内容が書けたら、次は締めくくります。
通知状・挨拶状の場合 まずは「■■■」申し上げます。
(「■■■」の部分は ご通知 お知らせ ご挨拶 ご案内など使い分けましょう!)
依頼文の場合 なにぶんのご配慮を願い上げます。
お詫び状の場合 何とぞ事ご賢察のうえお許しくださいますようお願い申し上げます。
謝絶の場合 誠に残念ですが、貴意に添いかねますのでご了承お願い申し上げます。
締めくくりがしっかりしていないと、なんだか頼りない文章になってしまいます。まとめの意味でもこの部分は意外に重要です。
時候の挨拶を使ったビジネス文書まとめ
ここまでのポイントを改めてまとめてみますね。
それぞれを組み合わせるとこのようになります。
拝啓
盛夏の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、
(内容)
まずはお知らせ申し上げます。
敬具
この例文は時候の挨拶一覧の中から7月のものを使いました!
初めから全てを考えるとわからなくなりますが、形式に沿って書くことによって簡単に、形式的に書くことが可能です。
伝えたい主文にしっかり時間を使うことができるように、前文の時候の挨拶などはささっと一覧から選ぶようにして書いていきましょう。
編集後記
時候の挨拶ってよく文章で見かけるけど、いざ書こうとすると忘れたと言うか?しっかり書けないと言うか、悩む部分です。
でもこうして時候の挨拶を月別の一覧にしてしまえばその中から選ぶだけなので超簡単。定番の挨拶を考えておけば迷うこともなくなります。
特に仕事上であれば悩む時間は惜しいもの。いい文章が時短で書けるように、一覧表を活用してくださいね。