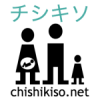4月になるとあちこちで鯉のぼりが上がり始めます。爽やかな気候の中で空を元気に泳ぐ鯉のぼり。
我が家のこいのぼりは、日当たりの良すぎたために風雨にさらされ色褪せた感じになってしまいました。
通っていた保育園では歌を習ったり、鯉のぼりを工作で作ったりして端午の節句を迎えていましたが、「鯉のぼりが端午の節句に飾られる理由や、その意味、色ごとの由来を知らない」という人も意外と多いのではないでしょうか。
私も息子が生まれるまで疑問にも思ってなかった鯉のぼりの意味や色の役割。鯉のお母さんについては衝撃の事実も・・。そのあたり、詳しく解説していきます!
カラフルなだけじゃない!鯉のぼりに込められた意味と色の由来は?

一般的な鯉のぼりのセットには、次のようなものが含まれています。
- 黒色の真鯉(お父さん)
- 赤色の緋鯉(お母さん)
- 青色の子鯉(子ども)
- 五色の吹き流し
実は、鯉のぼりのそれぞれの色には意味が込められています。また、吹き流しや矢車にも大切な役割があるのです。
そしてお母さんには謎も・・。順番に見ていきますね。
鯉のぼりの由来・・色の意味と込められた親の願い
鯉のぼりは、5月のこどもの日(端午の節句)に飾られるものですが、その背景には親の深い願いが込められています。
鯉のぼりの由来は、「幟(のぼり)」だけにそもそもは「旗」でした。戦のときに掲げる武者や家紋の入った大将の周りにいっぱいあるやつです。
江戸時代には、将軍家や武家が旗指物(家紋入りの旗)や幟(のぼり)を飾るようになり、これを庶民が真似して、鯉のぼりが誕生したと言われています。
もともと、端午の節句は厄払いの行事でしたが、鎌倉時代以降、武家の間で「尚武(しょうぶ)」という武を尊ぶ風習と結びつき、男の子の成長を祝う行事へと変化しました。
江戸時代に誕生した当初の鯉のぼりは黒い真鯉だけ。その後
- 明治時代:赤色の緋鯉が追加
- 昭和時代:青色の子鯉が登場
と、だんだんと家族の形に近づいていきました。
近年では、子鯉の部分に緑やオレンジ、ピンクなどのカラフル鯉のぼりも増えてきていますよね。地域によっては女の子の鯉も一緒に飾る家庭も増えてきています。形は変わってきても、家族を思う気持ちがどんどん増えていく感じがしていていいですね!
そんな歴史を持つ鯉のぼり。込められた意味は次のとおりです。
将来の立身出世を願う
中国の古い伝説の一つ、龍門伝説によると、激しい流れの滝「竜門」を登りきった鯉が、龍となって天に昇ったとされています。(この龍門伝説は「登竜門」という言葉の語源ともなったおはなし)
このことから、鯉は出世の象徴とされ、鯉のぼりは「子どもが将来、困難に負けず、大きく成長し、成功を収めるように」という願いが込められています。
潔く勇ましい子に育ってほしい
「鯉の水離れ」という言葉があります。
これは、水揚げされた鯉がまな板の上でも暴れず、静かにしていることから生まれた言葉です。
「まな板の上の鯉」という諦めの表現を連想するかもしれませんが、実は「動じずに受け入れる強さ」「最後まで堂々とした姿勢」を象徴するものとされています。潔い武士道精神・・肝がすわっているという感じですね。
このことから、鯉は「潔さ」を持つ魚として知られ、鯉のぼりには「困難に立ち向かい、堂々と生きる強さを持ってほしい」という願いが込められています。
家族の絆
そして、黒の真鯉(お父さん)は力強さ、赤の緋鯉(お母さん)は愛情、青の子鯉(子ども)は未来への成長という思いが込められています。
鯉のぼりの吹き流しの色と意味
吹き流しはちょっと脇役のように思われがちかも?な部分ですが、実はとても重要な役割を果たしています。
その最大の役割は、「厄災を祓い、神様をお迎えする目印になる」こと。そして「家・家族」を表しているのだとか。
色は中国の陰陽五行説に基づいています。一般的に赤、青または緑、黄、紫または黒、白で、構成されています。
- 青色:木(成長・発展)
- 赤色:火(情熱・活力)
- 黄色:土(安定・信頼)
- 白色:金(正義・純粋)
- 黒色:水(知恵・柔軟性)
この5色が揃うことで、万物のバランスが整い、邪気を寄せ付けないと考えられていました。どうしても鯉が目立ちますが、ここにも大事な意味があるのですね。
矢車と回転級の意味
鯉のぼりの一番上には、矢車と回転球がついています。それぞれの意味は次のとおり。
- 回転球:神様を呼ぶための目印
- 矢車:「カタカタ」と音を立てて、男の子の誕生を神様に知らせる役割
どちらも、子どもを見守る神様を迎えるために必要なものなのです。こちらも、鯉ばかりが目立っているけどきちんとした意味があったんです!
こいのぼり赤色のお母さんの謎
黒色がお父さんで、赤色がお母さん、他はこどもたち。想像通りという方が多いと思います。
でも鯉のぼりの色に関して、赤色はお母さんじゃない説もあるんです・・。
その説では、江戸時代の赤い鯉のぼり(緋鯉)は子供を表すものだったそうなんです!鯉のぼりにはお母さんがいない?たしかに「鯉のぼりの歌」の歌詞にもこうあります。
♪大きい真鯉はお父さん、小さい緋鯉は子供たち♪
歌にもお母さん居ない…そう思って聞くと本当だ!ってなってしまいました。ずーっと赤の鯉はお母さんだと思っていましたが、逆にどうして私はそう思ったんだろう?と感じ、掘り下げて調べてみました。
江戸時代に誕生した当初の鯉のぼりは黒い真鯉だけで、その後だんだんと家族の形に近づいていったと先ほども解説したのですが、お母さんが揃ったのは昭和になってから、ということなんです。
もともと真鯉1匹のみだった鯉のぼりには「家族」という考慮はなし。男性が強い時代だったせいもあったようです。
だんだんと時代が変わり、5色などカラフルなものが作られるようになり、家族構成となっていったというわけなんです。
だから今の時代を生きる私たちは、赤の鯉はお母さんと思っていて正解ということになりますね。
では真鯉って何なのでしょう?
これが、真鯉です。調べると「黒い鯉、普通の鯉」だそうです。たしかに普通の鯉ですね。お父さん鯉、意外と地味でした(笑)
ちなみに緋鯉は体色が赤または白を基調とする観賞用のものの総称だそう。
キレイでかわいい!っていう観賞用の鯉が緋鯉。昭和以降の鯉のぼりでは、お母さん役に抜擢です。
青や緑の鯉はさすがに珍しい部類だと思いますが、家族を表し、映える鯉のぼりにするために今はさまざまな色が使われているんですね。
鯉のぼりの意味と色まとめ
鯉のぼりの意味や色には、子どもの健やかな成長を願う深い想いが込められています。
江戸時代に生まれた鯉のぼりの風習は、時代とともに変化しながらも、今も多くの家庭で受け継がれていて素敵ですよね。
鯉のぼりのお母さんのことはちょっとびっくりだったけど、これはこれでこどもの日の話題にできると思います。
5月の空に元気よく泳ぐ鯉のぼりを見かけたら、その意味や色ごとの由来を思い出してみてください。しっかりと意味がわかっているとより有意義に過ごせると思います。