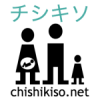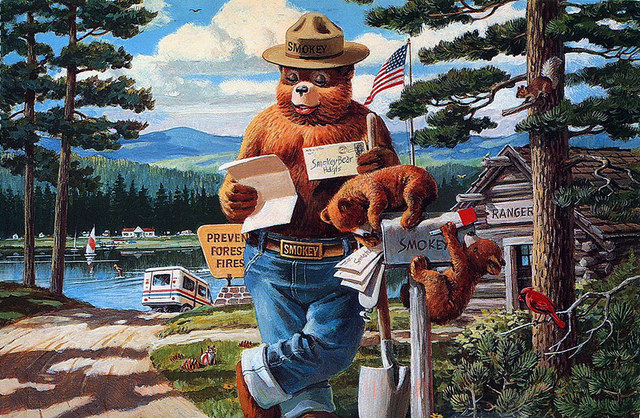天気予報やカレンダー、ラジオでも季節の話題になったときによく聞く夏至・冬至・春分・秋分。これらの言葉は、二十四節気とよばれる、季節を表す言葉です。
一年(365日)を太陽の軌跡が描く円とし、それを24つに分けて、季節の区切りを表す言葉として使用されていました。
言葉で書くとなんだかややこしくて分かりにくい部分もありますので、表を使ってひとつひとつ意味を見ていきましょう。
二十四節気の意味とは?
太陽暦を使っていた時代、季節の区切りを表すために、一年を24に分け、それをさらに「春夏秋冬」の4つのグループにしていました。
365日を24で分けたものだから、区切りと区切りの間は約15日間ということになります。
二十四節気の呼び方と意味は次の表の通りです。
| 立春 | りっしゅん | 2/4 | 春の始まり | 春 |
| 雨水 | うすい | 2/19 | 雪が雨に変わる頃 | 春 |
| 啓蟄 | けいちつ | 3/6 | 冬眠が開け、芽吹く頃 | 春 |
| 春分 | しゅんぶん | 3/21 | 昼と夜の時間がほぼ同じ | 春 |
| 晴明 | せいめい | 4/5 | 花が咲き、清らかな頃 | 春 |
| 穀雨 | こくう | 4/20 | 畑が整い始め、春の雨が多い頃 | 春 |
| 立夏 | りっか | 5/6 | 夏の始まり | 夏 |
| 小満 | しょうまん | 5/21 | 草木の成長 | 夏 |
| 芒種 | ぼうしゅ | 6/6 | 穀物の種まきの頃 | 夏 |
| 夏至 | げし | 6/22 | 一番昼が長い時期 | 夏 |
| 小暑 | しょうしょ | 7/7 | 暑さが本格的になる頃 | 夏 |
| 大暑 | たいしょ | 7/23 | 暑さが盛り上がる頃 | 夏 |
| 立秋 | りっしゅう | 8/8 | 秋の始まり | 秋 |
| 処暑 | しょしょ | 8/23 | 暑さの終わりの頃 | 秋 |
| 白露 | はくろ | 9/8? | 穂がでてきて秋を感じる頃 | 秋 |
| 秋分 | しゅうぶん | 9/23 | 涼しさ感じる頃。昼と夜が同じ長さ | 秋 |
| 寒露 | かんろ | 10/8 | 秋本番、菊が咲く頃 | 秋 |
| 霜降 | そうこう | 10/23 | 北や山に霜が降りる頃 | 秋 |
| 立冬 | りっとう | 11/7 | 冬の始まり | 冬 |
| 小雪 | しょうせつ | 11/22 | 冷え込みが激しくなってくる頃 | 冬 |
| 大雪 | たいせつ | 12/7 | 山には雪が積もる頃 | 冬 |
| 冬至 | とうじ | 12/22 | 夜が一番長い頃 | 冬 |
| 小寒 | しょうかん | 1/5 | 寒さの本番はこれから | 冬 |
| 大寒 | だいかん | 1/20 | 一年で一番寒い頃 | 冬 |
二十四節気は年によって、一日ほど前後する場合があります。
実際の感じ方よりも季節のズレを感じますね。 8/23に夏の終わりの頃っていうけどまだまだ暑いですよね。それはなぜでしょうか?
二十四節気の季節感
この二十四節気は中国からきたもので、日本とは少しズレが生じる場合が出てきました。
そこで日本でこの暦が導入された頃、土用や八十八夜、入梅や半夏や二百十日といった雑節とよばれる区切りをつけました。
日本での旧暦は、この雑節も入ったものを指します。
雑節(ざっせつ)とは?
24の季節の言葉ではズレが生じてきたことをきっかけにできた日本独特の暦が雑節です。
| 土用 | どよう | 1/7、4/17、
7/20、10/20 |
?立春・立夏・立秋・立冬の前18日 |
| 節分 | せつぶん | 2/3 | 立春の前日 |
| 彼岸 | ひがん | 春分・秋分の
前後3日間 |
春分と秋分の前後3日間のこと(7日間) |
| 八十八夜 | はちじゅうはちや | 5/1 | 立春から88日目 |
| 入梅 | にゅうばい | 6/11 | 芒種のあとの壬のの日 |
| 半夏生 | はんげしょう | 7/2 | 夏至から10日後 |
| 日 | にひゃくとおか | 9/1 | 立春から210日目 |
節分・彼岸なんかは良く聞く言葉です。
編集後記
知っている言葉もあったけど、知らない言葉もたくさん!日常的に触れてるはずの言葉だけど、知らずに毎日すごしていました。
まとめてみて、知ることができてとっても賢くなった気分になりました!