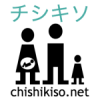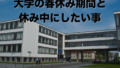3月3日のひなまつりは、女の子の幸せと健やかな成長を願う大切な行事です。
旧暦の3月3日は桃の花が咲く季節なので、「桃の節句」とも呼ばれています。
今では当たり前のように3月3日はひなまつりと思っていますが、由来や意味、ひな人形の歴史や飾り方、お祝いの食べ物など雛祭りについてについて詳しく解説します。
ひなまつりの由来
ひなまつりの起源は、古代中国の「上巳(じょうし・じょうみ)の節句」にさかのぼります。
旧暦の3月3日は「巳の日」にあたり、災厄や穢れ(けがれ)を払い清めるため、水で身を清める行事が行われていました。
この風習が日本に伝わり、人形に厄を移して川に流す「流し雛」の形となり、現在のひなまつりの基礎となりました。
そして「ひいな遊び」と結びついた
平安時代、日本の貴族の子女の間では「ひいな遊び」というおままごと遊びが流行していました。
この「ひいな遊び」と、先程の上巳の節句の風習が結びついたことで、ひな人形を飾る文化が誕生したんだって!
もともと厄払いのために水辺に流されていた人形でしたが、時代とともに精巧で華やかなものになっていきました。
これにより、「流すもの」から「飾るもの」へと変化していきました。
江戸時代には、ひな人形を家の中に飾る習慣が一般的になり、女の子の成長を願う行事として定着しました。
なぜ「桃の節句」なの?
「桃の節句」という名称は、旧暦3月3日頃が桃の花の開花時期にあたることに由来します。
さらに、桃の花は古来より魔除けや邪気払いの力を持つと信じられてきました。
また、桃の木は長寿の象徴ともされ、これらの理由からひなまつりには桃の花を飾る習慣が生まれました。
ひな人形の飾り方と片付け方
なんとなく雛人形を飾るものと考えてましたが、しっかりとひなまつりの由来がわかるとスッキリですよね!
次は雛人形の飾り方と片付け方をチェックしましょう。
飾る時期
ひな人形を飾り始める時期には明確な決まりはありませんが、一般的には 2月中旬から遅くとも2月末までに飾る 家庭が多いです。
「一夜飾り」(3月2日に飾ること)は縁起が悪いとされ、避けたほうが良いとされています。
一年に一度だけに、まあまあ奥に収納しているお家も多いと思います。出そうと思っているのに出していない・・そんなことも多いひな人形ですが、一夜飾りは縁起が悪いとされているし、せっかく出すならたくさん楽しみたいので、2月に入ったら出す気持ちでいるといいですね!
片付ける時期
ひな人形は、3月3日が終わったら 3月4日から2週間以内(3月中旬ごろまで) に片付けるのが一般的です。
「片付けが遅れると婚期が遅れる」とよく聞きますが、科学的な根拠はなく、整理整頓の習慣を身につけるためのしつけの一環と考えられています。
なので片付けに関してそこまで焦らなくて良いのですが、片付ける際には、湿気の少ない晴れた日を選ぶようにしましょう!カビや傷みにくいよう注意です。
ひな人形は何歳まで飾る?
これ結構悩みませんか?あれ?いつまで飾るものなんだろうって子供が成長したら感じるようになりました。
実は、ひな人形を何歳まで飾るかに明確な決まりはありません。
一般的には、 子供が成長し、進学・就職・結婚などの節目 で飾らなくなる家庭が多いです。成人しても「娘の厄除け」として飾ることもあります。
要は好きな時まで飾っても良い、と言うことになりますね。せっかくの雛人形ですから、楽しめるだけ楽しむと良いですね!
ひな祭りの食べ物
ひな祭りに食べられる縁起の良い食べ物を意味と一緒に簡単に紹介します!
- ちらし寿司:さまざまな具材が入ったちらし寿司は、彩り豊かでお祝いの席にぴったり。具材一つ一つにも願いが込められているんですよ!
- ハマグリのお吸い物:ハマグリは対の貝殻でなければぴったり合わないことから、良縁を願う意味が込められています。
- ひなあられ:色とりどりのひなあられは、四季を表し、一年を健康に過ごせるようにとの願いが込められています。
- 桜餅:春らしい桜の葉で包まれたお餅で、ひな祭りの定番スイーツです。
まとめ
ひな祭りは、古代中国の上巳の節句が日本に伝わり、貴族の遊びと結びついて発展した行事。
由来聞くと、長い時間をかけて定着した今の形がなんだかすごいと感じてきます。
現在では、女の子の健やかな成長と幸せを願い、ひな人形を飾ったり、縁起の良い食べ物を囲んだりして祝う伝統行事として親しまれています。
地域によって異なる風習があったり、家庭によって様々な形がありますが、家族で日本の文化を楽しめるといいですね。