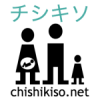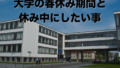土用の丑の日
といえば、「鰻(うなぎ)」です!・・これは知ってるんだけど、土用の丑の日がいつなのか?ということに私が気づくのはスーパーのチラシでした。
うなぎが目立つな・・土用の丑か!っていう感じで(笑)
しかし二十四節気のことを知ってから、「土用」とはいつなのかがわかりました。

今回は今年の土用の丑の日はいつなのか?そして意味やなぜ鰻を食べるのか?を記事にしました!せっかく(高価な)鰻をたべるのだから、食卓で意味を語ってみてください♪
2025年の土用の丑の日はいつなの?
土用は実は年に4回あります。土用といえば夏のイメージがありますが、2025年の日にち4回とも全て紹介しておきますね。
※鰻を食べる習慣があるのは主に夏の土用です。
2025年(令和7年)
- 冬の土用の丑の日・・1月20日・2月1日
- 春の土用の丑の日・・4月26日
- 夏の土用の丑の日・・7月19日・7月31日
- 秋の土用の丑の日・・10月23日・11月4日
丑の日2回あるのはなぜ?
よくみると2回ある場合がありますね!
例えば、2015年は夏の土用の丑の日は2回ありましたが、2016年は1回、2017年は2回ということになります。2018年も2回。2019年は1回でした。
見事にバラバラで、その年によって回数が変わるんですね。牛の死は12支→12日周期です。詳しくは後述しますが、土用は18日間なので、その間に2回くる場合があるんです。
ちなみに、2回あった場合は大体、1回目がメインになります。
18日間?ん?となっていると思いますので、次に土用の丑の日の意味をまとめます!
土用の丑の日の意味とは?
にも記事にしていますが、「土用」というのは年に4回あります!
「土用」とは二十四節気の雑節で
「立春」・「立夏」・「立秋」・「立冬」の前18日のこと。
これを具体的に言うとそれぞれこうなります。(年によって日数は多少の変動あります)
- (立春)1/17からの18日間
- (立夏)4/17からの18日間
- (立秋)7/20からの18日間
- (立冬)10/20からの18日間
そして、丑の日は上記のそれぞれ18日間のうちの「丑」に当たる日で、暦の上で12日に一回まわってきます。
12支の「ねー、うし、とら、うー」ってやつですね。昔、12支は日ごとにも割り当てられていました。
まとめると、
土用の18日間のうち、12日に一回くる丑の日に当たる日を土用の丑の日と呼びます。
このように数えていくと、土用は18日間、12支で数えるので、丑の日が2回くる場合もあることになるのがわかりますよね。
2回目の丑の日は「二の丑」と呼びます。丑の日が2回ある場合、スーパーなどで大々的に扱われるのは大体1回目の丑の日です。
さて、うなぎは美味しいので大好きですが、そもそもなんでうなぎを食べるようになったのでしょう?次は歴史を見てみましょう!
夏の土用の丑の日に鰻を食べる理由
さて、上記を見ると4回も土用があるのに、なぜか夏の土用にだけ鰻を食べるのが有名ですよね?一番有名な説をご紹介します。
実は鰻の旬は冬なんです。
だけど夏にも鰻を売りたくて、鰻の蒲焼屋さんは困っていました。
発明や陶芸、日本最初のコピーライターとして有名な平賀源内が丑の日に「う」がつく食べ物がいいという迷信から、
「土用の丑の日に鰻を食べて元気になる」
とのキャッチコピーを考え、土用の丑の日に鰻を食べる習慣を作ったと言われます。
これにより夏には売れなかった鰻がたくさん売れるようになり、夏の土用の丑の日にはウナギ!が定着したという説が有力です。
うちの食卓でも、土用の丑の日だから・・という理由で鰻を食べるという贅沢ができちゃってます(笑)さすが日本最初のコピーライターですね!
編集後記
土用の丑の日についてまとめてきました。
実は年に4回あり、18日間のうち12日間に1回巡ってくる丑の日ということがわかりました!
うなぎは高価だけど、土用の丑の日のご飯の時間はぜひ、おいしい鰻とたのしい土用の丑の日のうんちくで盛り上がりたいですね!
鰻は実際に栄養価が高く、夏バテなどにもぴったりなので、食べて元気を出しましょう!